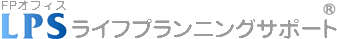祇園祭
2022/06/28
今年は3年ぶりに祇園祭山鉾巡行が行われます。
学生時代に毎年参加していただけに思い入れがあります。
何度かこの祭りについて紹介してきましたが、私が曳いていた「岩戸山」について少し触れてみたいと思います。
山鉾巡行は神輿が通る道をあらかじめ清めておく、もしくは厄災をもたらす疫神を鎮めるために練り歩いた、と言われています。
その鎮魂災と共に誕生したのが「鉾」で、かなり後になって見せ物として登場したのが「山」だそうです。
「天岩戸を開いて天照大神の出現される神話に取材した山である。山とはいえ鉾と同じ車をつけた曳山である」と、京都市は説明しています。
鉾と山の違いは屋根の上だそうです。
鉾は「真木(しんぎ)」という屋根の上に約20mの長い柱が立っていて、そのてっぺんに「鉾柱」があり、それぞれの鉾の象徴が飾られています。
山は真木ではなく松の木が飾られ、「真松」と呼ばれています。
山鉾はその形から、数の多い順に「舁山(かきやま)」「鉾(ほこ)」「曳山(ひきやま)」「船鉾(ふねほこ)」「傘鉾(かさほこ)」に分類されます。
岩戸山には天照大神、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、手力雄尊(たぢからおのみこと)の三体のご神体が安置されています。
日本神話の天岩戸、国生みを色濃く表した曳山なのです。
岩戸山を曳いていた時はたいした知識を持ち合わせていなかったのですが、このように調べてみると日本神話から繋がる由緒ある山を曳いていたことに改めて感銘を受けています。
例年梅雨が明ける頃の7月17日前祭(さきのまつり)で岩戸山もご覧ください。